3.記念物 3-1.史跡
常夜灯 1基
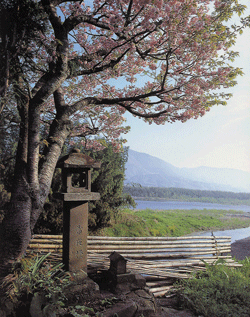

- 指定 つるぎ町
- 分類 記念物
- 種別 史跡
- 所在地 つるぎ町半田字小野249番地2先
- 指定日 平成3年3月28日
- 所有者または管理者 旭地域
文政9年(1826)に小野連中が建立した。和泉砂岩の石材を用い、高さ1.85メートル、「日」と「月」の明かり窓をくり抜いている。
小野浜港は江戸時代中期より、吉野川帆船交通の発達により発展し、半田川流域の玄関口としてにぎわった。
この常夜灯は大正3年(1914)3月25日の鉄道開通まで88年間、川灯台としての役割も果たした。 なお常夜灯には、「文政九戌年五月吉日」と彫られている。
三王堤防 1件

- 指定 つるぎ町
- 分類 記念物
- 種別 史跡
- 所在地 つるぎ町貞光字大須賀
(貞光工業高校グラウンド北方) - 指定日 昭和51年5月11日
- 所有者または管理者 つるぎ町
明暦3年(1657)に構築された吉野川右岸の石巻堤で、元は藤森堤と呼ばれた。堤防の天幅約6メートル、底幅約15メートル、高さ4.5メートル、長さ約524メートル、工事責任者は貞光代官・原喜右衛門。
この工事は、当時の貞光村を中心に近隣8ヵ村の住民の賦役によってなされたが、過酷を極め、人力をもってしては賄いきれぬ大工事であった。見積もりの誤差もあり、原代官は責により切腹、従者2名も殉死。明治26年(1893)三王神社創設に伴い三王堤防と呼ばれるようになった。
また、東端山政所武田助左衛門は直訴、御法度により入牢申しつけられ獄死した。
江ノ脇古墳 1基

- 指定 つるぎ町
- 分類 記念物
- 種別 史跡
- 所在地 つるぎ町貞光字太田西446番地
(江ノ脇薬師堂上方) - 指定日 昭和51年5月11日
- 所有者または管理者 つるぎ町
6世紀後半~7世紀初期。高い段丘の先端にあり、堆土は低い。古墳後期の円墳で横穴式石室をそなえている。直径22メートル、石室は全長5.77メートル、玄室(奥行き2.17メートル、幅1.74メートル、高さ2.24メートル)と、長さ3.05メートルの羨道部から成る。天井部は3枚、緑色結晶片岩板石、奥壁一枚石。その他、切石3.05メートル。羨道は東向き。勾玉・須恵器坏・馬具(杏葉)・刀装具・鉄鏃・鏡などが出土している。
西山古墳 1基

- 指定 つるぎ町
- 分類 記念物
- 種別 史跡
- 所在地 つるぎ町貞光字西山55番地1
- 指定日 昭和57年4月28日
- 所有者または管理者 永井喜一郎
貞光駅の西南方、平地より80メートル高い急斜面にある。付近はクヌギ林で墳丘上に立石がある。円墳で横穴式石室を持っており、6世紀後半~7世紀初頭のものと思われる。
羨道は東向きである。玄室長2.25メートル、同幅1.81メートル、同高1.58メートル、天井部は5枚の緑色結晶片岩。側壁は片岩の割石積み。中間は狭く幅36センチ、堆土は低い。直径推定10メートル。出土遺物は須恵器の坏蓋、長・短頸壺、提瓶などがあった。
中野のろう石(大理石)

- 指定 つるぎ町
- 分類 記念物
- 種別 史跡
- 所在地 つるぎ町一宇字中野7053番地
- 指定日 平成23年12月13日
- 所有者または管理者 中野 一男
徳島県下でも、ろう石の産地として古いといわれている中野のろう石(大理石)。明治33年採掘、国会議事堂建設に使用する大理石として検討された。昭和初期閉山以来そのままの状況で現存していた良質の石材である。
