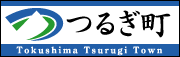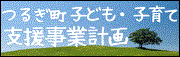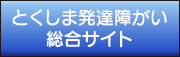父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳※再認定の請求が必要)までです。
手当を受けられる方は
次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母および養育者(所得制限があります。)
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
次のような場合は手当は支給されません
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している
- 父または母が婚姻している(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父または母の配偶者に養育されている
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改訂されました
これまで公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
手当額
| 児童数 |
手当月額 全部支給 |
一部支給 |
|
|---|---|---|---|
| 1人 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
|
| 2人 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 | 加算 |
| 3人~ | 6,450円 | 6,440円~3,230円 | 加算 |
※一部支給は、所得に応じて10円刻みで算定されます。
※この額は、物価スライドの適用により、変更されることがあります。
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 本人 | 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
| 0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
※2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は、
- 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
※3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が※2の場合にはそれぞれ)を加算した額。
手当を受けるには
児童扶養手当を受けるには、申請が必要です。離婚や配偶者の死亡により新たに受給資格が生じたときには、速やかに認定請求の手続きをしてください。
認定請求に必要なもの

- 印鑑
- 請求者及び児童の戸籍謄本
- 請求者及び児童の住民票謄本
- 預金通帳(普通預金で、請求者名義のもの)
- 年金手帳の写し
- 請求者の個人番号が分かる書類
※対象児童、同一住所地の扶養義務者等の個人番号の記入も必要 - 請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
- ※その他、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。
支払時期
2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます
- 1月(11~12月分)
- 3月(1~2月分)
- 5月(3~4月分)
- 7月(5~6月分)
- 9月(7~8月分)
- 11月(9~10月分)
※支払日は、各月の11日です。支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。
現況届
受給者は、毎年8月中に現況届を提出することになっています。この届は、年1回、手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※対象者には別途通知いたします。
一部支給停止措置について
平成14年の法改正で、手当支給後5年経過または支給要件発生後7年経過者の方については、手当額が1/2になることとなりましたが、次の項目に該当する方々は、窓口へ必要書類を提出していただくことによって、減額されない場合があります。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
ご注意ください
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受給されていると、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居を含みます。)
- 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託等)
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき(年金額が児童扶養手当額より高い場合)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき